要約
■ 治らない難病 煩悩
・ 欲 怒り ねたみそねみ
→ 欲とは…なければ欲しい、あればもっと欲しいという心。満足がない。欲のせいで不平不満から離れられない
→ 怒りとは…欲が邪魔されたときに湧き起こる心。欲しいと思ったときに誰かに妨げられると、なぜ邪魔したんだと腹が立つ。怒りでイライラムカムカして幸せになれない。
→ ねたみ そねみ 恨み…欲を邪魔した相手が目下の人だったら怒りをぶつける。目上の人だったら怒りをぶつけられないので恨みや憎しみになる。また、人が頭角を現すと面白くないからねたむ、そねむ。
・ 煩悩はなくすことができないから治らない難病
・ 親鸞聖人は私たちを煩悩具足といわれる
→ 煩悩具足とは煩悩100%でできているという意味
凡夫というは無明・煩悩われらが身にみちみちて、欲もおおく瞋り腹だち、そねみねたむ心多く間なくして、臨終の一念に至るまで止まらず消えず絶えず (親鸞聖人)
・ 治らない難病を抱えている限り幸せになることはできないのか?
→ そうではない
■ 治る難病 死後が暗い心
→ 無明業障の病ともいう
・ 死後が暗いとは死んだら先がわからないということ。古今東西のすべての人が死後が暗い心を抱えている。
・ 死後が暗いと今が憂鬱になる
→ 未来が暗いと現在が暗くなるのと同じ
・ この暗い心は本願他力によって治すことができる
・ 死後が暗い心が全快したことを信楽という
→ 死後が暗い心はいつ治るのかというと、平生の一念で完治する。
・ 信楽 = 無碍の一道
→ 煩悩が障りにならなくなった世界。煩悩が喜びに転じることから煩悩即菩提という。
☆ 氷と水のごとくにて 氷多きに水多し 障り多きに徳多し
→ 氷と水の関係は、氷が小さければ溶けた水も小さい。氷が南極大陸ほど大きければ溶けた水も大きい。
→ 氷 = 煩悩
→ 水 = 喜び
・ 信楽になるためにはどうすればいいか?
→ 仏法は聴聞に極まる
感想
すべての人は2つの難病にかかっているという。それは煩悩と死後が暗い心。煩悩は治らない難病で、死後が暗い心は治すことができる難病だという。この2つの難病は仏教をきかないと知ることのない病気だ。病院にいって診察されてわかる病気ではない。そこが仏教独特の考え方だと思う。
煩悩は死ぬまでなくすことができない。滝に打たれても、座禅をしても煩悩はなくならない。死ぬまで煩悩と付き合っていかなければならない。
しかし、煩悩があるままで幸せになることができる。それが死後が暗い心を治すことだ。信楽の身になることができれば、煩悩が障りにならなくなった世界に出られるという。煩悩が喜びに転じるといわれる。
本当にそんな世界があるのかと疑いたくなるが、もしそんな世界があるならその身になってみたい。それはお釈迦さまが説かれたことだから、本当だと思うが簡単に納得できることではない。疑いの心はなくならないが、自分の目で確かめてみたい。
仏法は聴聞に極まる。

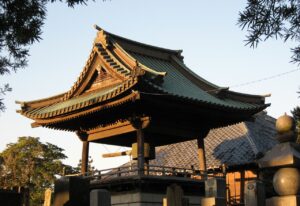






コメント