書籍
はじめに
我が師、野村克也監督なら、どうしていただろう。そんな想像をせずにはいられませんでした。厳密には「元監督」なのですが、僕にとっては、この呼び方が、今もいちばんしっくりするので、本書では「監督」で通させて欲しいと思います。2015年の日本シリーズ、パ・リーグ王者のソフトバンクは、僕が19年間お世話になったヤクルトを4勝1敗で退け、2年連続日本一に輝きました。ヤクルトが「よく一つ勝てたな」と思えるほど、ソフトバンクの強さは抜きん出ていました。野村監督は、強さには「圧倒的な強さ」と「相対的な強さ」の2種類があると言います——。
野村克也 宮本慎也
1935年、京都府生まれ。南海ホークス(現・福岡ソフトバンクホークス)に入団後、65年に戦後初の三冠王に輝く。70年から選手兼任監督。80年に45歳で現役を引退。MVP5回、首位打者1回、本塁打王9回などタイトルを多数獲得。89年に野球殿堂入り。90年にヤクルトスワローズの監督に就任し、4度のリーグ優勝、3度の日本一に輝く。阪神タイガース、東北楽天イーグルスの監督などを歴任。
1970年、大阪生まれ。高校野球の名門・PL学園から同志社大、プリンスホテルを経て、95年、ヤクルトスワローズに入団。2004年アテネ五輪、08年の北京五輪では日本代表の主将をつとめる。12年に2000本安打と400犠打を達成し、13年に42歳で現役を引退。ベストナイン1回、ゴールデングラブ賞10回。野村監督には入団4年、指導を受けた。

プロセスなき成功は、失敗よりも恐ろしい
やはり人間性を磨くということは、技術とはまったく関係がないようで、長いスパンで見ると必ずやリンクしているものです。体を鍛える、技術を磨くという行為は、どんな競技であれ、少なからず過酷なものです。丈夫で、大きな心の器が出来上がっていないと、いずれ壊れたり、あふれ出たりしてしまうものなのです。野村メモにはこんな言葉があります。
<失敗してだめになった人より、成功してだめになった人の方が多い>
<失敗する恐ろしさよりも、いい加減にやって成功することの方が、もっと恐ろしいのだ>
失敗してだめになった人より、成功してだめになった人の方が多いというのはちょっと意外だった。成功することはかならずしもいいこではない。むしろ成功したことで慢心やうぬぼれてしまいだめになってしまうということだろうか。だからこそ人間性を磨く必要があるのかもしれない。
強者と弱者の戦い方の違い
ひとつの商品でシェアを獲得すれば業績が安定するだけでなく、その評判が拡散し、他の商品にもいい影響を及ぼします。そうして少しずつ会社を成長させていけばいい。大事なのは、まず何らかのジャンル、どこかの地域で、一位を獲得することなのです。
菊池雄星や大谷翔平を生んだ岩手県の花巻東高校の佐々木洋監督は就任当初、「トイレ掃除でも、あいさつでも、授業態度でも、できるところから日本一になっていけば、野球もそれに引っ張られていつか日本一になれるんだ」と言って今の強豪に育てたと聞きましたが、その発想なのです。
ランチェスター戦略では、強者は集団戦、弱者は個人戦に挑むべきだと教えているそうです。
何らかの分野で一位を取るこで、他の分野にもいい影響を及ぼす。まずは得意なことを極めることが大事だという。僕自身のなかでは、散歩習慣を極めることを意識している。誰にも負けないくらい歩く習慣を続けることで、他のことを習慣化する能力が身についた。ブログを書く習慣も、歩く習慣がなかったらおそらくできなかったと思う。
「野球依存症」になれ
努力を努力と意識しているうちは、一流とは言えない。努力を持続させるコツがひとつある。それは努力を習慣化させることだ。「習慣は才能より強し」である。
生活の中の実に40%までもが習慣的行動だという。つまり、脳を使っていない。心理学用語で、習慣化させることを「自動化」と表現する。自分の生活の中に習慣として組み込み、頭を通さず行動に移せるようにするわけだ。頭を通すから、面倒くさいとか、しんどいとか、負の感情を引き起こし、練習を始めるハードルをどんどん上げてしまう。
努力を習慣化させることができれば、面倒くさいとか、しんどい、と思うことはなくなるという。確かにそうだなと思う。でもそこまで習慣化させるまでが大変なことだ。習慣化する前に努力をやめてしまうことが多い。僕自身も勉強を習慣化しようと思っても、なかなか続かない。面倒だなという気持ちがでてきてしまう。そこを乗り越えて習慣化できるように自分を磨いていきたい。






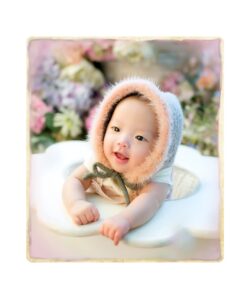

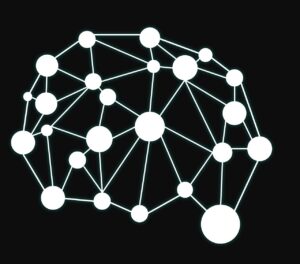
コメント