なぜ心を重視するのか
約1000年前の平安時代中期に源信僧都といわれるかたがいた。その源信僧都がこのように歌われています。
よもすがら
仏の道に入りぬれば
わが心にぞ
たずね入りぬる
夜も徹して(一晩中)仏道修行していると、いつのまにか自分の心の中に尋ね入っていくようだという意味です。仏教を聞くということは、自分の心を見つめることであり自分の心の中に入っていくこと。
なぜ仏教は心を重視するか。
仏教には三業という言葉があります。業とは行いという意味です。インドでは業のことをカルマといいます。三つの業とは、
身業 体でやる行い
口業 口で喋る行い
意業 心の中で思う行い
この三つの行いが私たちの幸せ、不幸せを決める行いです。この三つの行いの中で特に重視するのが意業(心の行い)です。
なぜならば、心で思っていることが口や体にでるからです。その人が喋っていることは心の中で思っていることです。その人が何かやることも心の中で思っているからです。
だから、心の行いが大事になってきます。心によってその人の人生は決まります。
仏道修行
仏教の仏道修行とは、行を修めるとかきますが行とは善い行いのこと。善い行いを修めて悟りを開こうとすること。行には体の行いもあれば口の行いもあるが、最も重視されるのは心の向きです。心が修行のときは大事だと仏教では教えられます。清らかな心で実行する行、これが求められます。
仏教では五逆罪というのがあります。親を殺す罪のことです。親を殺すとは手にかけて殺すことだけじゃない。親鸞聖人は、次のように言われています。
親をそしる者をば五逆の者と申すなり
親のことを心で、邪魔だ、早く死んでくれ、と思えば心で殺していることになる。心で殺しているということは縁が来たらやってしまうということです。
仏教は法鏡だとお釈迦様は言われました。法とはダルマといって真実という意味です。だから法鏡とは真実の鏡ということです。
真実の鏡とは心を映す鏡です。これが仏教なのです。
親鸞聖人の求道
親鸞聖人の仏道修行はどうだったか。親鸞聖人は9歳から29歳まで20年間比叡山で修行をされた。その中で親鸞聖人の右にでるものはいないというくらい学問も修業もされた。
体の行い、口の行い、の仏道修行は親鸞ほど立派にしているものはいないと言われた。しかし、誰にも知られていない心の中の行いはどうであろうかと大変苦しまれた。
悪性さらにやめ難し心は蛇蝎のごとくなり
親鸞聖人はご自分の心は悪性だと言われた。それをやめようと思ってもやめられない。蛇の心とは人を恨んだり、ヒトの幸せを妬んだり、人の不幸をクスクス面白がる醜い心。
蝎の心とは思い通りにならないと、あいついなくなってくれればいいのに、あいつ死んでくれればいいのに、という怒りの心。
どんな人に対しても抱くゾッとする蛇や蝎の心だと親鸞聖人は言われた。
修善も雑毒なるゆえに虚仮の行ぞと名づけたる
善い行いはするけれど全部計算ずくで、これだけ善いことしたらこれだけ返ってくるだろう、みんなに褒めてもらえるだろう、と思っている。純粋な善ではない。
だから、そらごと、たわごと、の偽善ではないかと親鸞聖人は言われる。心の中を見たときに私のような者は救われないと絶望され比叡山を降りられた。
そして法然上人に遇われ、そんな私を阿弥陀仏の本願によって救われることを知り救われた。
感想
仏教では心の行いを一番重視するという。体の行いも口の行いも心がもとになっているから。だから心が問題になってくる。しかし、心の中で思うことは蛇や蝎のようにゾッとすることを思ってしまう。誰にも知られたくないことだが、すべての人の心はそうなっている。
心の行いを徹底的に見つめると、自分は悪しかできないと思える。とても清らかな心など持っていない。そんな自分が救われるはずもないとも思えてくる。しかし、そんな悪人を相手に救うと誓われたのが阿弥陀仏の本願だという。
阿弥陀仏の本願誠だったと知らされるまで聴聞を続けていきたい。

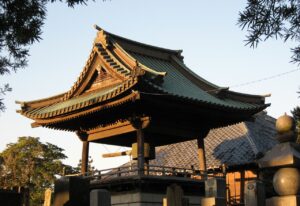






コメント