最近、運動していないな、と感じたら家の外を歩いてみましょう。歩くことは脳にとってとてもいい刺激になるし、気分転換にもなります。
運動不足になっていると、気分の落ち込みや、やる気の低下につながります。そんなとき一番簡単に始められることが歩くことなのです。
歩くのは一回30分以内で十分です。30分以内でも脳内にエンドルフィンやセロトニンという幸福ホルモンがでるのでやる気アップや幸せを感じることができます。
はじめに
私は、BTUというストレスケアのスクールで代表を務めています。ストレスケアというと、カウンセリングのような心にアプローチする方法を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、同時に体にもアプローチすることで、さらに効果を発揮します。その方法のひとつとして、私が生徒たちにすすめているのが、大きな歩幅で歩くことです。ひどい肩こりや不眠を抱え、子供の不登校に悩む女性がいました。彼女は「物事を深く考えすぎてしまう自分の性格が、2人の子どもに悪影響を与えているのでは」と心配してスクールへやってきました。私は、カウンセリングやリラクセ―ション法でのケアを行いつつ、彼女に「歩くとき、大きな歩幅を意識してみて」とアドバイスしました。それからというもの、彼女はなるべく歩くように、そして歩幅を大きくするように心がけていました。すると、1か月ほどたったころ、子どもから「私たちも大人になったら、お母さんがいつも行っているところに行きたい」と言われたそうです。

本書の著者 美野田啓二 BTU(バランスセラピー Univ.)代表 1956年生まれ、早稲田大学卒、日本大学大学院前期博士課程修了。1989年「身体からアプローチするカウンセリング・心理学」バランスセラピー学を創始する。脳を活性化する歩き方などのセルフケアは、ストレスや疲労から短期間で回復できる方法として幅広い分野から高い評価を得ている。
その1
脳へたくさんの酸素を送れれば、脳の機能をアップさせられる。その方法として有効なのが有酸素運動です。歩幅を大きくすることは、運動習慣がない人でもすぐに始められますし、長時間続けやすい運動です。
有酸素運動、とくに歩幅を大きくして歩くことは、習慣にしやすい。僕自身も歩くことを習慣にしているが、走ることと違い、終わったあと肩で息をするほど疲れることはないのがいい。また明日も歩きたいなと思えるので長く続けることができる。
その2
ソクラテスやプラトン、カント、ニーチェなど、散歩を習慣にしていた哲学者は大勢います。京都の有名な「哲学の道」は哲学者の西田幾多郎が、思索にふけりながら散策していたことから命名された散歩道です。偉大な先人たちは経験から、歩くことが脳に及ぼす影響を理解していたのかもしれまん。
僕自身、考えごとをしながら歩くことがあるが、自分の考えがまとまることもあるし、まとまらないこともある。しかし、考えごとをしながら歩くというのがとても楽しいと感じる。一人で歩いていても全然苦にならないし、つまらないとも思わない。

その3
やる気や集中力を生み出すには、神経伝達物質であるセロトニンが必要不可欠です。物事に興味を持ったり、集中して取り組むためには、歩いて、セロトニンの分泌を促せばよいのです。
なぜ歩くことでやる気や集中力がでるのか、その理由はセロトニンが分泌されるからだという。セロトニンには気持ちを穏やかにさせる効果もある。だから歩いたあとは爽快感があり、気持が前向きになることが多いのも納得がいく。歩けばセロトニンがでるということを知っている人は、日々の生活習慣を変えることができる。
本書には、歩くことは脳にどのような影響を及ぼすかや、体や心にはどんな効果があるのかが書かれている。本書を読めば、今すぐにでも歩きたくなること間違いない。
その他のウォーキングの書籍

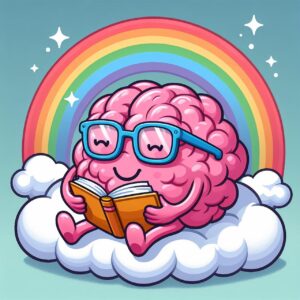
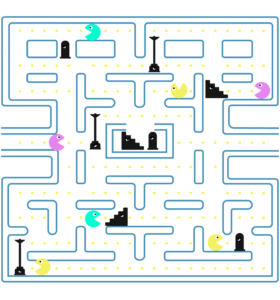










コメント