要約
■ 中学生のメンタル不調が増える本当の理由
ℚ 中二でうつが増えるのはなぜですか?
Ā 私(樺沢)の仮説がある。いじめも中学生が多い。高校生や大学生になるといじめはすごく減る。そういう研究がある。高校生ぐらいになってくると脳の発達が進んでくる。
・ 小学生、中学生は誕生日が早生まれなど一週間違うだけで学年が変わる。同じ学年でも11カ月20日長く生きている人間と同じクラスになる。成長が進んでいる子供と遅れている子供のギャップが大きい。
・ 本来の成長発達でも学年差で発達の未熟さが生まれる。個々人による発達の遅れもある。
・ 発達障害の人が将来どうなっているか調べた研究がある。約半分の人は普通に生活している。幼稚園や小学校の頃に発達が遅れている子供がいるが、それは少し遅れているが20歳までに追い付いて、普通のレベルになる人が多い。それが子供の頃に発達障害と診断されてしまう。
・ 小中学生の頃はできる子とできない子の差が大きくでる。人間関係やコミュニケーション力は小中学生で大きく進化する。その中でコミュニケーション能力の高い子は友達をたくさん作れる。
・ コミュニケーション能力が低い発達が遅れ気味の子は友達が作れない。そうすると仲間外れにされたり、いじめられやすくなる。同じ学年でもうつになりやすく、ストレスを多く抱える。
・ ある程度発達が進むとストレスをうまく解消できるようになる。
◇ 中学生はギャップの世代。不登校も中学生が多い。メンタルの問題がでやすい時期。身の回りで起きるトラブルにうまく対応できない。いわゆる適応障害のようなものを起しやすい時期。慎重に見守る必要がある。子供が発達障害かもしれないと慌てる可能性があるが高校生くらいになると、いい大学に進学する人も多くなる。
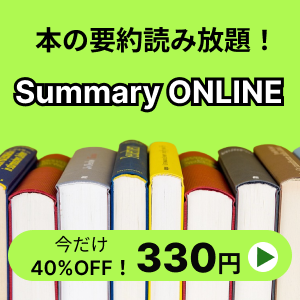
■ 不登校から脱出する! 自己治癒の5つのカギ
ℚ 昨年の10月から不登校になりました。最近は週に1回は学校に行けるようになりました。前日は絶対に行くと決めても朝になると嫌な気持ちになり行けません。アドバイスをお願いします。
Ā 5つのカギをやっていくと登校できるようになります。
その① 自分や他人を責めない
・ 学校に行けないとダメな人間だといって自分を責める。あるいは他人を責める人もいる。自分をいじめる人のせいだ、先生が相談に乗ってくれない、○○のせいで学校へ行けなくなった。自分や他人を責めるのは受け入れられないから。
・ 受け入れていない人は「自責・他責・怒り・落ち込み」を示す。受け入れられない限り次に進めない。自責や他責は受け入れられない人の行動。受け入れると良くなっていく。学校に行けなくなったことを「しょうがない」と受け入れることが重要。
その② 朝散歩をする
・ 不登校をメンタルの原因だと考える。メンタルの原因は治らない場合が多い。「学校って好きじゃないんだよね」「学校へ行ってもつまらないんだよね」「学校へ行っても友達いないんだよね」それを不登校の原因にした場合、学校が楽しくならない限り戻れない。現実やメンタルを調整する必要はない。
・ 不登校を治すためには体を整えればいい。不登校の人の多くは朝起きられない。昼間まで寝ていると夜に眠れなくなる。ゲームやネットで夜更かしする。
・ 夜更かしする → 朝起きれない → 学校に行けない、この悪循環に陥る。規則正しい生活をしていて不登校に陥る人はいない。
その③ 朝食をとる
・ 不登校の人は朝食をとらない人が多い。朝食をとらないと体内時計がリセットされない。朝散歩は脳の体内時計がリセットされる。朝食をとることで全身の体内時計がリセットされ、意欲がわく。
・ 朝散歩ができない場合は日向ぼっこがいい。家の中で最も日が当たる場所で15分~30分座っているだけでいい。
その④ スマホ・ネット・ゲームを手放す
・ ネットやゲームは楽しいので長時間やってしまう。家にいても暇つぶしができてしまう。特に夜更かしをしてしまう。不登校で朝起きられず昼間まで寝る人は、夜にずっと勉強をしている人はいない。
・ 深夜にゲームやスマホを長時間すると体内時計が狂う。読書などをすれば眠気がでてくる。夜中のゲームやテレビやスマホが不登校の間接的な原因になっている。
・ 夜11時に寝て朝7時に起きる人はそうそう不登校にならない。
その⑤ リアルな人間と時間を過ごす
・ 人と会ったり話したりする。不登校だと友達とも会わず、親とも話をせずに部屋に引きこもる。人と会って話すだけでオキシトシンがでる。オキシトシンとは癒しの物質。オキシトシンがでると脳疲労を癒してくれる。
・ 孤独はメンタルに対して毒になる。人と会って話すことが癒しになる。人とコミュニケーションをとることで良くなっていく。自分と似たような環境の人と話せるとラクになる。
◇ 重要なのはあなたの性格が悪いわけではない。あなたの人間性が不登校を作ったのではない。体内時計のズレが不登校の重要なカギ。体内時計さえ整えば気分は上向きになる。
■ 子供のスマホが危険な脳科学的な理由
ℚ 中一の息子がいます。小学生の頃からスマホを欲しがり、みんな持っているといっていましたが、トラブルに巻き込まれたくないので買っていません。大人でさえSNSのトラブルで自殺する人がいるのに、子供だともっと危険性が高まるのではないかと思っています。子供にスマホは必要ですか?
Ā 精神科医の私が考える子供のスマホの危険性は、依存症になりやすいこと。
・ 小中学生くらいの子供の頃は脳の中の抑制系の成長が不十分。スマホやゲームが楽しいとき、我慢したりやめさせることが未熟でできない。
・ 大阪府スマホサミットのアンケートの結果には、高校生の3分の1がスマホの依存症レベルであるという結果が出た。また、ある調査によると女子校生の6.8%が15時間以上スマホを使っていることがわかった。女子のほうがメンタル疾患の罹患率が高い。男子に比べて3倍ほど高い。
・ スマホの長時間利用とメンタルの状態が関連している可能性が高い。
◇ 子供にスマホやゲームを与える場合、制限できるかどうかが重要。利用時間のルールを親子で決める。それを守れるかどうかが大事。

感想
中学生は多感な時期である。学校での人間関係がうまくいかくて孤独を感じることがある。あるいは勉強にもついていけなくなり、人生に意味があるのだろうか、と考えるようになる時期だと思う。
僕自身は中学生の頃は人間関係がうまく築けなかったことと勉強が嫌だったこともあり、人生ってなんのためにあるのか、と考えることが多かった。その心境が当時大ヒットしたアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の主人公達と似ていてとてもハマった。中学時代は楽しい思い出よりも、辛く寂しい思い出のほうが多い。
中学生の頃にもし朝散歩をしていたらどうなっていたか。もっと学校が楽しくなっていたかもしれない。あれから時は流れ、今は40代を超えているが朝散歩の効果はばつぐんにいいことを実感している。朝散歩のおかげでメンタルは安定し人間関係にも役立っている。これからも朝散歩は続けていこうと思っている。








コメント