何か物事がうまくいかないとき、そこには必ず原因がある。野球でいえば負けたときや失敗したときがそれにあたる。そうなったとき徹底的にプロセスを見直す必要がある。
どういう過程でそうなったのかを検証しなければ、結果は変わることがない。逆に言えば負けや失敗しときの原因さえわかれば、後はどうすればいいのかがわかるので安心できる。
負けや失敗をすることは気分のいいものではないが、苦しくても原因を見つけることができたとき勝ちや成功の結果が待っている。
はじめに
「負けかたについてかいてください」 出版社から要請を受けたとき、正直、腹が立った。半世紀以上、勝負の世界で生きてきた。そこでは勝つことのみが評価され、敗者は去るのみである。選手のときも、監督のときも、シーズンを迎えるにあたって誓ったことはただひとつ——「全勝してやる!」、それだけだ。 毎試合勝つつもりで、全力で挑んだ。負けることなど、勝負に臨むに際して考えたことは一度もなかった。どんなに劣勢に立たされている試合であっても、「絶対逆転してやる」という気持ちを失わなかった。勝負の世界に生きる人間にとってはあたりまえのことで、「負け」は私がもっとも嫌いな言葉のひとつだ。「そんな私に、『負けかたについて書け』とは何事か!」 最初はそう思ったのである。だが——。 考えてみると、私の人生はある意味、負け続けだった。何をするにしても、すべてが負けからスタートしている。最初からうまくいくことなど一度もなかった。
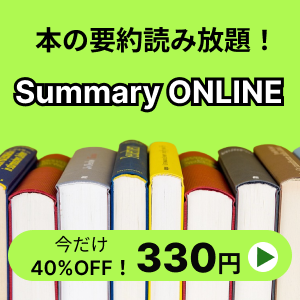
本書の著者 野村克也 1935年、京都府生まれ。54年、京都府立峰山高校卒業。南海(現・福岡ソフトバンク)ホークスへテスト生として入団。4年目に本塁打王。65年、戦後初の三冠王(史上二人目)など、MVP5度、首位打者1度、本塁打王9度、打点王7度。ベストナイン19回、ゴールデングラブ賞1回。70年、監督(捕手兼任)に就任。73年、パ・リーグ優勝。のちにロッテオリオンズ、西武ライオンズでプレー。80年に45歳で現役引退。90年、ヤクルトスワローズ監督に就任。4度優勝(日本一、3度)。99年から3年間、阪神タイガーズ監督。2002年から社会人野球・シダックスのゼネラル・マネージャー兼監督。06年度、東北楽天ゴールデンイーグルス監督就任。
その1
なぜ、失敗や負けから学ぶことが重要なのか。「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」と、私はよくいう。勝利したとき、「どうして勝つことができたのか」については、真剣に振り返らないことが多い。(中略)しかし負けに「不思議の負け」はない。半世紀以上、プロ野球の世界に身を置いてきた経験から、これは断言していい。負けには、必ず負けにいたった理由がある。たとえ偶然のように見えても、あるいは不運のように見えても、突き詰めれば必ずそれを招いた原因があるはずなのだ。
勝負の世界において、負けたときにただ落ち込んではいられない。その原因を究明することが大事だという。「負けに不思議の負けなし」という言葉はとてもいい言葉だと思う。なぜ負けたのかを徹底的に考えることが次の勝負に活かされる。仏教の教えのなかにもどうしてそのような結果になったのか、原因をあきらかにみることを諦観という。勝負の世界と仏教の教えが通じるところがありとても面白い。
その2
失敗や負けは、過信やうぬぼれを戒め、謙虚さ、素直さを教えてくれる。というより、謙虚に、素直にならざるをえない。現実に成功しなかったのだから、過信しようがないし、うぬぼれようがないのである。「自分はまだまだだ」と思うしかない。中国の『書経』にこういう言葉がある。「満は損を招き、謙は益を受く」満足すれば妥協を呼び、妥協を呼べば進歩も止まるが、謙虚な気持ちを忘れなければ、多くの疑問が生まれ、もっと高みを目指して努力するようになる。
失敗や負けから謙虚な気持ちが生まれる。そして謙虚な気持ちからもっと高みを目指そうと努力するようになるとノムさんはいう。勝ちつづけることで傲慢な人間になってしまったら、人として残念な人になってしまう。傲慢になることでその人は転落していき、やっぱり負けを経験する。どうしたって負けを経験しない人はいない。負けから何を学べるかが、その人の成長に大きく影響してくると思う。

その3
失敗や負けの原因を検証・究明する際は必ず、「正しいプロセスを経ていたか」をチェックしなければならない。「野村野球とはどういうものか?」 私のもとで選手やコーチを経験した者はよく訊かれるらしいが、私ならば、こう答える。「プロセス重視の野球」「プロフェッショナルの”プロ”とはプロセスの”プロ”」——ことあるごとにそういっているほどだ。
正しいプロセスを経ていれば、たとえ今回はうまくいかなくても次はうまくいく確率が高くなる、そんなことを聞いたことがある。しかし正しいプロセスをつくるのもまた大変なことだと思う。負ける原因は間違ったプロセスということだから、どこをどう変えれば正しいものになるのか検証するのは難しい。一口に正しいプロセスといってもそれを発見するのは並大抵のことではない。
本書では野村克也さんの「負け」のなかで得られた考え方が中心になって書かれている。「知将」と呼ばれたノムさんならではの哲学となっていてとても面白く勉強になる。ぜひ読んでみることをおススメします。
その他の野村克也さんの書籍








コメント