人との関係がうまくいかなくなるとき、それは距離の問題が関係しているかもしれません。知り合って間もないときは新鮮に感じます。お互いの事を知る楽しさを感じ、距離は縮まっていきます。
しかし、ある程度仲良くなってくると相手の嫌な面が気になりだしてきます。仲良くなることで楽しさを共有できるようになりますが、相手に対する不満も感じやすくなります。
相手に対する不満の気持ちが高まってきたら、それは近づき過ぎているサインです。少し離れてみることが大事です。離れることで相手に対する不満は減り、また仲良くしたいという気持ちが戻ってくるでしょう。
はじめに
「人と人は近づいたほうがわかり合える」「仲がよくなればなるほど理解し合える」 みなさんはそう思っていませんか? じつは、そこには一つ「落とし穴」があります。人間関係のトラブルは、ほどんどの場合、近すぎることから起こります。アカの他人とは通常、心を悩ませるトラブルになることは少ないと思います。 母と娘。恋人同士。会社の同僚や上司。メル友。隣人。このような関係はみなおたがいの距離が近いですね。距離が近すぎると、見なくてもいい相手の「欠点」や「わがまま」や「無理解」「無神経」などが見えてしまいます。そこで、メールの返事がすぐ返ってこないと不安になったり、自分を無視していると思ったりもします。すると「わたしがこんなに尽くしているのに、いったいどういうことなんだ」とか「あんなことを言っているが、本音はどうなんだ」とか、考えなくてもいいいことを考えてしまいます。その結果、関係に隙間風が吹き込むことになります。 人と人との関係には「ほどよい距離」というものがあります。

本書の著者 和田秀樹 1960年大阪生まれ。東京大学医学部卒、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て、現在は精神科医。国際医療福祉大学教授。ヒデキ・ワダ・インスティテュート代表。
その1
心理学の世界でとてもよく知られている寓話に「ヤマアラシのジレンマ」というのがあります。2匹のヤマアラシが寒いからもっと近寄って温め合いたい、でも近すぎるとおたがいのトゲが刺さって痛いというジレンマを、「ほどよい距離」を保つことで乗り越えるという話ですが、人間関係の場合「寒さ」は孤独感とか、依存心とか、あるいは独占欲といった複雑な心の動きから生まれる。
この「ヤマアラシのジレンマ」の話しを僕自身はTV版アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のなかで知った。あまりに近い関係というのはケンカになりやすいし、自分の思い通りにしたくなってしまうから不満がでやすい。「ほどよい距離」が大事だとわかる。
その2
好きな人が多いと好かれようとしなくて済むということ。周囲に好きな人ができてくると、その誰とでもほどよい距離を保ちながら長く付き合うことができます。1人にだけ執着することはなくなるでしょう。
僕自身友達がいなかった学生時代に誰か一人でもいいから仲よくなりたいと思っていて、一人に執着していたらウザがられてしまった。おそらく見下されていたと思う。今では友達も増えて「ほどよい距離」のとりかたがわかってきたので一人に執着することはなくなった。
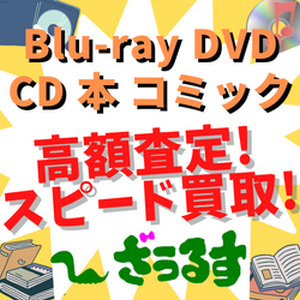
その3
身近な人とは距離の分だけ濃いつき合いになりますが、濃い関係というのはおたがいに相手の嫌なところも見てしまいますから、一度苦痛に感じるとどんどん嫌悪感が膨らんできます。もし「ちょっとくっつきすぎたかな」とか「惰性でつき合っているな」と感じる相手や仲間がいるようでしたら、べつに嫌いじゃなくても少し距離を置いてみましょう。
これは僕自身の経験であることだが、仲良くなった友達と毎月一回は会っていることがあった。最初は楽しかったが、だんだん毎月会うのが義務のように感じられ、それほど話すこともないのに会っていたら苦痛になってきた。だからその友達と毎月会うことをやめにした。一年くらい経ってから会ってみると、話すことも多くとても楽しかった。少し距離がある関係のほうが「また会いたいな」と思うことができ長くいい関係が続くと思う。
本書では人との「ほどよい距離」を保つことの重要性が教えられている。読み終わったらすぐに実行したいことばかりであり、知識として知っておくだけでもずいぶん人間関係に役立つことだと思う。
和田秀樹さんのその他の書籍








コメント